 保育士なこ
保育士なこ2歳児を育てていてお困りのお母さん。
魔の2歳児?
超絶イヤイヤ期?
- 毎日何をするにもイヤイヤばかりでもうへとへと。
- 思い通りにならないとすぐにイヤイヤ、泣きやまない。
- イヤイヤにどうやって対処したらいいのか分からない。
もうこんな状況に疲れた。と悩んでいませんか?
2歳児はイヤイヤ期真っ只中ですよね。
個性もありますが、みなさん一度は子どものイヤイヤに苦労したことがありますよね。
このブログは保育士歴15年以上の、2歳児クラスを何度も担当したことがあるベテラン保育士が書いた記事です。
この記事を読むとイヤイヤ期の2歳児への対処法が分かり、毎日の育児が少し楽になること間違いなしです。
今の状況から抜け出してみませんか?
ぜひ最後までお読みください。
この記事で解決する悩み
- 2歳児が思い通りにならないと泣く原因
- 2歳児が思い通りにならないと泣く対処法
- 2歳児がすぐに泣きやまないときに注意するポイント
- 2歳児イヤイヤ期いつまで続くの?
以上の悩みを解決する記事を用意しました。
2歳児が思い通りにならないと泣く対処法
2歳児がすぐに泣きやまないときに注意するポイント
イヤイヤ期を乗り越えるためのオススメの本はこちら
2歳児が思い通りにならないと泣く原因とは

 保護者
保護者魔の2歳児っていわれるけれど、どうして思い通りにならないと泣くの?
 保育士なこ
保育士なこ感情のコントロールがまだ難しい時期だからです。
理由がいくつかあるので説明していきますね。
自分の方を向いてほしいアピール
2歳児はまだまだ甘えたい時期。
ズボンを履けたり、靴を履けるようになっても、
「できない~」
といって甘えたくなるのです。
甘えて大人に応じてもらえることで、心が満たされ大人を信頼していきます。
「この人は自分の甘えをどれだけ受け止めてくれるかな?」と試している部分もあります。
保育園で一人の子が「できない~」となると、その隣の子も真似をして「できない~」といってみたりするのは、日常の光景です。
わがままをいいたくて泣く
2歳児ってわがままをいいたくなる時期なんです。
2歳児がわがままをいうのは、自己主張をする方法のひとつとして、自分の欲求や感情を表そうとしているからです。
2歳は言葉の発達がすすみ、自分の欲求や感情を伝えることができるようになる時期。
しかし十分なコミュニケーションスキルを持っていないため、わがままな行動や言葉を使うことがあります。
2歳は自分自身が中心で、他人の思いや感情を理解することが難しいです。
そのため自分の欲求や思いを優先しようとするのは自然なことでしょう。
成長とともに感じる気持ち
2歳児は言葉で少しずつ伝えられるようになる時期ですが、まだまだ自分の思いを全て言葉で伝えることはできません。
言葉で伝えられないから自分の思いが伝わらず、思い通りにならないと泣いてしまうのです。
それは立派な成長の証です。
自分の気持ちがあること、それは自我の芽生えで、そこからイヤイヤ期を乗り越えて自立に向かっているのです。
眠気などの機嫌が悪い場合
2歳児はまだまだ生理的欲求で泣く部分もあります。
眠たくてぐずぐず、おなかがすいてぐずぐず泣いてしまうことも。
もっと寝たかったなど寝起きの機嫌が悪い場合もありますよね。
大人だったら眠たくてもおなかがすいても我慢ができますが、2歳児はまだまだ我慢ができません。
生理的欲求で泣いている場合は満たしてあげましょう。
発達障害の可能性も視野に
- 生理的欲求を満たしても泣く、気持ちを満たしても泣きやまない。
- 気持ちの切り替えが極端に苦手。
- 何をやっても泣き続ける。
- 他の子どもと比べて明らかに泣き方がおかしい。
そんな傾向がみられたら、地域の保健師に相談してみましょう。
子育てでどうにもできない辛さはあります。
一人で悩むことにいいことはありません。
他人を頼ることも必要ですよ。
障害児保育について知りたい方はこちらの記事もお読みください。
→障害児保育をするうえで大切なこと。接し方や配慮のポイントを徹底解説!
2歳児の子どもをもつ実際の声

Twitterからの実際の声
 保育士なこ
保育士なこ2歳児を育てる上で苦労しているお母さんはたくさんいますよ。
あなただけではありません。
ここ数日むすめのイヤイヤがひどい。基本のお返事が「やだ」。思い通りにならないと泣く。風呂も入りたくないらしい。魔の2歳児、楽勝だなと思ってたが2歳9ヶ月にきてだいぶしんどい。
— ゆみ (@bingobird1977) April 13, 2011
何が大変って、ジブンデ!ジブンデ!の2歳を追っかけ回すのが大変でした。思い通りにならないとひっくり返って泣くし。。。ザ☆2歳児。って感じ。
— moca (@caffemocha) May 5, 2017
イヤイヤ期に片足を突っ込んでるひーしゃん。まだまだ序の口なんだろうけど思い通りにならないとすぐに泣いて嫌になる😞言うこと聞いてやってくれることのほうが多いんだけどスイッチが入ると甘えて泣く😩💦こんなもんか。魔の2歳児😈
— さ (@tomatokonnyaku) September 25, 2019
イヤイヤ期で悩んでいるお母さんはたくさんいます。
同じ悩みを持つ人がいるだけで安心感がありますよね。
2歳児クラスを受け持ったことがある保育士の声
 保育士なこ
保育士なこ私は2歳児クラスを何度も受け持ったことがある保育士です。
2歳児イヤイヤ期。保護者の悩みもたくさん聞いてきました。
私自身も子育て経験者です。2歳児って大変ですよね。
あれもイヤ。これもイヤ。
さっきまでよかったのに、またイヤ。
子育てでは頭を悩ませたこともたくさんあります。
2歳児クラスを受け持つとイヤイヤ期真っ只中。
まだ自分の言葉で上手く伝えられない時期なので、保育士として大事にしていることの一番は共感です。
どんなにその子が悪くても、わがままをいっていても”共感する”。
共感することでその子の気持ちが満たされます。
「そうだったね」
「○○したかったんだね」
この言葉だけでいいのです。
気持ちが満たされるだけで子どもは大人を信頼するでしょう。
信頼関係ができると、なにがあってもこの人は味方だと感じるようになります。
その信頼関係が子どもの自立へと導いていくのですよ。
2歳児が思い通りにならないと泣く対処法7選
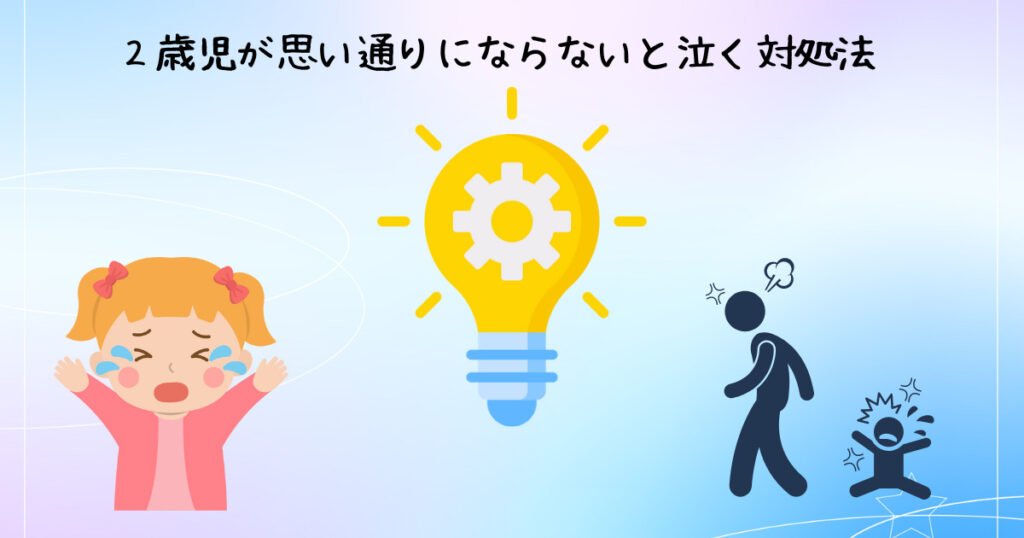
 保護者
保護者泣いたらどうやって対処すればいいの?
 保育士なこ
保育士なこ対処法はいくつかあります。その時に応じていろいろな対応方法を試してみてくださいね。
子どもの気持ちを受け止め共感する。
保育士の私が考える一番の対処法は共感です。
どんなことに対しても共感してもらえることで、子どもは気持ちが落ち着くのです。
「そうだったんだね」
「いやだったね」
など子どもの気持ちを代弁してあげることがいいでしょう。
代弁とは
子どもの気持ちを代わりに大人がいってあげることを代弁といいます。
共感し続けていくことで、子どもが成長するなかで、他人の気持ちを考えられるようになっていくのです。
抱っこして気持ちを落ち着かせる
抱っこはお母さんができる一番の魔法。
抱っこをすると身体が触れ合い、心も気持ちも満たされます。
お母さんの抱っこほど、子どもが安心できる場所はありません。
子どもはお母さんの抱っこが大好きなのです。
泣いてないてどうしようもない時は抱っこしてあげましょう。
「抱っこ」+「共感」が最高のタッグです。
抱っこしながら子どもの気持ちに寄り添ってあげましょう。
気持ちが落ち着くまで様子見
思い通りにならなくて泣いている子どもは、気持ちが高ぶっています。
泣いて発散し気持ちが落ち着くまで様子見をすることも方法のひとつです。
落ち着くと上手く気持ちを切り替えられることも。
要求を聞いてほしい、抱っこしてほしいのに何もしないのは様子見ではなく放置です。
その時々の子どもの状態をみて、判断するようにしましょう。
他のことに興味が向くように声をかける
泣いていて気持ちの切り替えが上手くできない子どもには、気をそらせることも必要です。
抱っこして外の景色を見せたり、遊びに誘ったりしながら、気持ちを落ち着かせるようにしましょう。
泣いていても違うことに興味を持てば、切り替えがスムーズになることもあります。
いろいろな方法を試しながら探っていきましょう。
子どもが納得するまで寄り添う
子どもがしたかったことを大人が先にしてしまったり、いつもの順序じゃないと怒ったり、この時期の子どもにはよくあることです。
大人は面倒で大変でも、子どもが納得するまで寄り添うことも必要です。
行為をはじめからやり直し、自分ですることで納得してから気持ちが切り替わることは、保育園の園児でもよくあることです。
子どもの気持ちに寄り添ってあげましょう。
約束事を決める
イヤイヤ期はどんなことでも泣いて訴えようとすることもありますが、大人はここまでは許せる線引きを決めておくことが大事です。
危険なことやしてはいけないことがありますよね。
約束事はきっちりと決めて、子どもには誠実な態度で向き合いましょう。
ルールはいつも同じことが絶対です。
約束が変わると子どもは混乱します。
夫婦で子育てについての約束事を、話し合っていくことも大切ですね。
選択肢を与える
思い通りにならないと泣いてしまう2歳児。
選択肢を与えることは保育園でもよく使うポイントです。
「あれもイヤだ」
「これもイヤだ」の2歳児ですが、
「どっちにする?」
といわれると、「こっち」といってくれるものなのです。
大人でもどちらも嫌だけど、どちらかだったら選んでしまいますよね。
子どもにも使えるとっておきの方法です。
いろいろな対処法がありますが、かならずしもこれをすれば上手くいくという方法はありません。
7つの対処法を上手く組み合わせながら、あの手この手で子どもに向き合っていくことが大切です。
切り替えが早い子も遅い子もいて、個々に応じて方法も変わってきます。
保育士はいつもいろいろな方法を試しながら、その子にとっていい方法を見つけていきます。
お母さんもこれができたら鬼に金棒!
ぜひ試してみてくださいね。
2歳児のイヤイヤ期におすすめの本はこちら
2歳児がすぐに泣きやまない時に注意するポイント(放置はだめ?)

 保護者
保護者対処法は理解したけれど、注意するポイントはある?
 保育士なこ
保育士なこイヤイヤ期に限らず子どもを育てていくなかで大切なことがあります。
ぜひ参考にしてください。
放置して何も対処しない
対処法の中に「気持ちが落ち着くまで様子見」とありましたが、放置とは別物です。
子どもが望んで時間を置いた方がいい場合と、要求しているのに聞かずに放置することは、お母さんにとっても子どもにとってもいいことはありません。
イヤイヤ期にイライラしてしまうお母さんの気持ちも分かりますが、お母さんも一呼吸おいたら、子どもの気持ちに寄り添ってあげるようにしましょう。
気持ちを受け止めない、寄り添わない
子どもの気持ちを聞いてあげたり寄り添わないことは、余計にイヤイヤを長引かせるだけです。
子どもは気持ちを共感してもらうことにより、安心して落ち着くことができるのです。
いつまでたってもイヤイヤが続いてしまうだけですよ。
気持ちを代弁してあげましょう。
叱っていうことを聞かせる
イヤイヤで泣いているからといって頭ごなしに叱るだけでは逆効果です。
子どもは怖いから、叱られるから泣きやむしかないという認識になります。
子どもを叱ってばかりだと大人を信頼することができません。
怯えからいうことを聞くようになったとしたら、今後の成長に悪影響をおよぼす可能性がありますよ。
自立した大人へと育てていくためには絶対に避けるべきことです。
約束を守らない
子どもとの約束事、家庭でのルールをつくることは必要です。
いつも同じルールでなかったり、今日はよくて違う日はダメなど、約束事がコロコロ変わると子どもは混乱します。
約束していたのに守ってくれなかったら、大人同士でも不信感ですよね。
子どもも同じですよ。
明らかな子どものSOSに気づかない
明らかにイヤイヤ期だけではない泣き方、他の子どもと比べて切り替えが難しいなど、一番に気づいてあげるのは親のあなたです。
発達遅延や障害のある子どもは泣いて訴えることで、大人にSOSのサインを出しているのですよ。
少しでも違うな、心配だなと感じたら、市の保健師や相談機関に連絡してみましょう。
自分だけで悩む必要はありませんよ。
子どもの発達遅延などには早期発見し、必要な療育を受けることが子どもにとって一番良いことです。
抱え込まずにお母さんもSOSを出して人に頼っていきましょうね。
 保育士なこ
保育士なこお母さんも心の余裕がなくなる前に人に頼っていくことが親と子どもにとって一番いい方法ですよ。
地域に無料の相談機関もたくさん設置されていますよ。
2歳児イヤイヤ期いつまで続くの?

イヤイヤ期は一般的に2歳から3歳の間が多いですが、個人差があります。
この時期は子どもが自己主張をしようとする時期であり、自立心や意思表示の発達の過程です。
イヤイヤ期の長さは子どもによって違いますが、一般的には数ヶ月から1年ほど続くことも。
3歳頃になると、子どもの言葉や社会性の発達がすすみ、イヤイヤ期は徐々になくなっていくでしょう。
イヤイヤ期の間、子どもは自分の意思を主張しようとするために、反抗的な態度をとることがあります。
親はしんどい時期かもしれませんが、子どもの成長過程として受け入れることが大切です。
 保育士なこ
保育士なこ子どもに対して根気強いかかわりと愛情を伝え、いつかなくなっていくものと気持ちを大きくして、向き合っていくようにしましょう。
2歳児が思い通りにならないと泣く対処法5選。イヤイヤ期を乗り越える方法を解説のまとめ
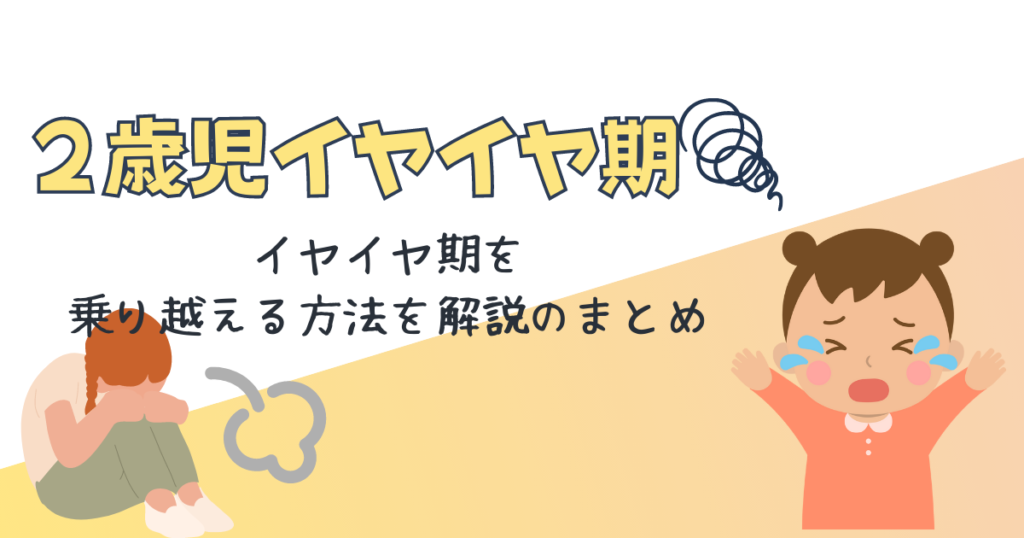
2歳児が思い通りにならないと泣く対処法
2歳児がすぐに泣きやまないときに注意するポイント
イヤイヤ期を乗り越えるためのオススメの本はこちら
2歳児のイヤイヤ期は親にとってしんどくて辛い時期かもしれませんが、子どもの成長過程だと割り切って付き合うようにしましょう。
どんなに辛くても子どもの気持ちに共感し続けることで、子どもは安心して成長していくでしょう。
何も話さなかった赤ちゃんがイヤイヤをいえるようになっただけでも、立派な成長ですよね!
長い目で、大きな心で子育てをしていきたいものですね。
保育士でありお母さんである私も、子どものイヤイヤ期にはイライラしたものです。
お母さん自身が子どもと離れて休息をとったり、お父さんに任せたりすることも、子どもと気持ちよく向き合うことができます。
辛い時は一人で悩まずに誰かに相談したり、気持ちを発散していきましょうね。
2歳児イヤイヤ期におすすめの本はこちら
保育士におすすめの記事はこちら





コメント