 保育士なこ
保育士なこ保育士に向いている人ってどんな人なんでしょう?
保育士を目指すに当たって、自分は保育士に向いているんだろうかと考えたことはありませんか?
また、保育士をしている中で、自分は保育士に向いていないかもしれない、と悩んだことはありませんか?
このブログは保育士歴15年の保育士に向いている筆者が書いた記事です。
保育士に向いているかだけでなく、向いていない人の特徴や保育士に向いている人になれるコツも合わせてお話していきます。
この記事で解決する悩み
- 保育士に向いている人の特徴9つのポイントって何?
- 保育士歴が長い人の経験談が知りたい
- 保育士に向いていない人の特徴とは?
- 保育士に向いている人になれるコツが知りたい!
以上の悩みを解決する記事を用意しました。
- 保育士に向いている人の特徴はたくさんあるが、人間得手不得手がある
- 保育士に向いていない人でも努力次第で向いている人になれる
- 保育士に向いていないのではなく、職場が自分に合っていない可能性がある
- 保育士としての経験を通して保育士に向いている人になれる!!
保育士に向いている人の特徴9つのポイント!
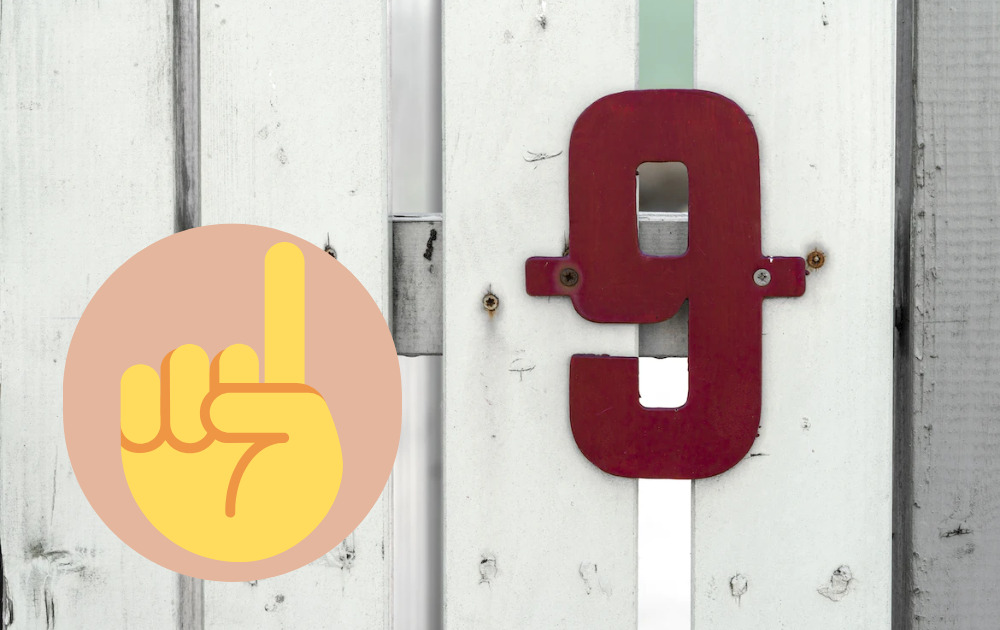
子どもが好き!
保育士として子どもが好き!!なのは当然のことです。
ただ、”子どもが好き!”だけでは保育士の仕事が務まらないのも事実です。
子どもは素直なだけではありません。
成長の過程で保育士を困らせることも多々あるからです。
そんな所を全部受け止められて、なおかつ”子どもが好き”な人は保育士に向いています。
体力
保育士に体力は必須です。
元気いっぱいの子どもと一緒に過ごすのはもちろんですが、子どもの病気をもらいやすいためです。
子どもの菌は非常に強いです。
特に1年目の保育士は免疫がないからか病気をもらいやすいです。
経験と共に免疫もついてどんどん強くなってきますよ。
日頃から、睡眠、食事を十分にとって、強いからだ作りを心がけましょう。
コミュニケーション能力
保育士はさまざまな年代の方とかかわっていく職業です。
職員や保護者、地域とのかかわりもある園もあります。
そこで必須になってくるのがコミュニケーション能力です。
人と話すことが好き、人とかかわることが苦手でない方は保育士として向いていますよ。
ポジティブ思考
ちょっとしたミスや失敗などで弱気にならず、「次、頑張ろう!!」と思えるポジティブ思考の人の方が保育士としては、働きやすいです。
先輩保育士の指導や保護者からのクレームが今まで一度もない!という人はいないからです。
指導もプラス+に変えていける人は保育士に向いています。
指導はあなた自身の成長のためと感じることが大切です。
子どもの命を守る責任がある仕事です。責任感が強い人は保育士に向いています。
感受性が豊かな人
 保育士なこ
保育士なこ保育士にとって感受性が豊かなことは大事なポイントです。
子どもの気持ちに寄り添うことや、子どものちょっとした喜びに共感してあげることが大切です。
子どもの気持ちに共感したり、受け止めてあげることで、子どもの成長を助けることにもつながります。
子どもの「なぜ?どうして?」にも応えたり、一緒に考えることで子どもとの信頼関係が築きあげられますよ。
忍耐力
忍耐力とは・・・困難や逆境など辛い状況でも耐え、目標に向かって努力し続ける力の事です。
保育士として働いているといいことばかりではありません。
困ったことや大変なこともあります。
その中で困難に立ち向かい、乗り越えていくことで、自分自身の成長にもつながります。
また、子どもと接する中で、なかなか保育士の話を聞いてくれない子や、不安定な子など、いろいろな子どもがいます。
そのような子どもと毎日一緒に過ごし、どうしたら安定して園生活を送れるか、このかかわり方がいいかな、など日々考えながら保育していく必要があります。
忍耐力が強い人は保育士に向いていますね。
観察力が優れている
保育士にとって観察力は必須です。
子どもが昨日できなかったことが、今日できるようになったりなど、子どもたちの日々の様子を把握していく必要があります。
子どもの「できた!」の気持ちに寄り添い、共感していくことが何よりも大切です。
乳幼児の噛みつきやひっかきなど、子どもたちがケガをなるべくしないよう十分な見守りが必要で観察力が必要です。
見通しが立てられる
保育士は毎日、毎週、毎月と子ども達の日々の成長を助けるために、計画を立てて保育をしています。
こうなってほしい姿をイメージし、先の見通しを持って日々保育することが求められているからです。
また、子どもの遊び方などを観察し、トラブルが増えてきたら、保育室の環境づくりを変更したり、成長に伴って玩具の種類を変えたり、増やしたりしながら先の見通しをもって保育しています。
文章を書くのが苦でない
IT化が進んでいる世の中ですが、保育士はまだまだ根強く自分の言葉で文章を書くことが多いです。
日々の連絡帳、日誌、計画、記録など、書類仕事は山積みです。
保育士として経験していく中で、文章の書き方や記録の書き方も上手になってきますが、元々文章を書くのが好きな人は保育士に向いています。
保育士として向いているポイントはいくつもありますが、経験の中で培っていける部分もすごく多いです。 今、できないからといって、保育士をあきらめる必要はありませんよ。
保育士に向いている筆者の経験談と思い

筆者の私も最初から保育士に向いていたのか?と考えるとどうでしょう。
学生の時に実習に行ったときは、実習先がきつすぎて辛い思い出もあります。
実際、実習に行っただけで、保育士に向いていないと感じ、保育士になることをあきらめた同級生もいます。
今、言えることは保育士として働いていく中で、保育士に向いている分野を培っていったこともすごく大きくあります。
1年目はそれなりに先輩方の指導もたくさん受けたし、保護者からのクレームもありました。
社会人としてのルールもたくさん学びましたね。
しかし、それなりに耐えて、自分自身の成長につながると感じて日々保育してきたお陰で、今の自分があります。
今でも上記の9つのポイントを全てもっているかと考えると即答はできませんが、日々努力しているのは確かです。
そして経験する中で保育士に向いているなと感じられてきているのもあります。
一緒に働いている保育士の中で、この人は保育士に向いていないポイントが多いなあと感じることもありますが、結果その人が保育士として楽しく子どもたちと接し、楽しんで働いているのなら、不正解なんてないと考えています。
保育士に向いていないとあきらめるのではなく、保育士に向いている人になれるよう日々努力して経験を重ねていけばより素敵な保育士になれること、間違いなしです!!
保育士に向いていない人特徴5つ

 保育士なこ
保育士なこ実際保育士に向いていない人の特徴はどんなものがあるのでしょうか?
保育士を目指していく中でどうしても必要なこともあります。
詳しく話していきますね。
人見知り
保育士は人とかかわる仕事です。
子どもや保育士、保護者とも関係を築いていく必要があります。
人間関係を築くのが苦手だったり、初めての人と話すのが苦手な人は厳しいかもしれません。
体力
向いている特徴にもありましたが、元気な子どもと毎日を過ごす仕事。
体力が必須です。
病気ももらいやすいですし、赤ちゃんを抱っこしたり、女性が多い職場なので、重い荷物を運ぶこともあります。
神経質
保育士になりたい人で神経質の方はなかなかいないかもしれませんが、実際、赤ちゃんのよだれであったり、おむつ替えをしたり、汚物の処理をすることもあります。
神経質で極度のキレイ好きな人は難しい仕事です。
消極的
子どもの前で話したり、行事では保護者の前で話したりする場面がたくさんあるので、消極的で人の前に立つことが苦手な方は、大変かもしれません。
また、職員会議など、意見を求められることも多々あります。
手先の器用さ
手先の器用さは人それぞれ向き、不向きがありますが、保育士にとってピアノを弾いたり、製作物を作ったりなどは、仕事の一つですね。
得意分野は人それぞれなので、保育士同士で得意分野を分け合って仕事をするのもいい方法ですが、不器用さんや、そもそも製作物が苦手な人は難しいです。
向いていない人の特徴を話しましたが、努力次第では、短所を長所に変えていくことも可能ですよ。 経験と共に培っていきましょう!!
保育士に向いている人になるコツ
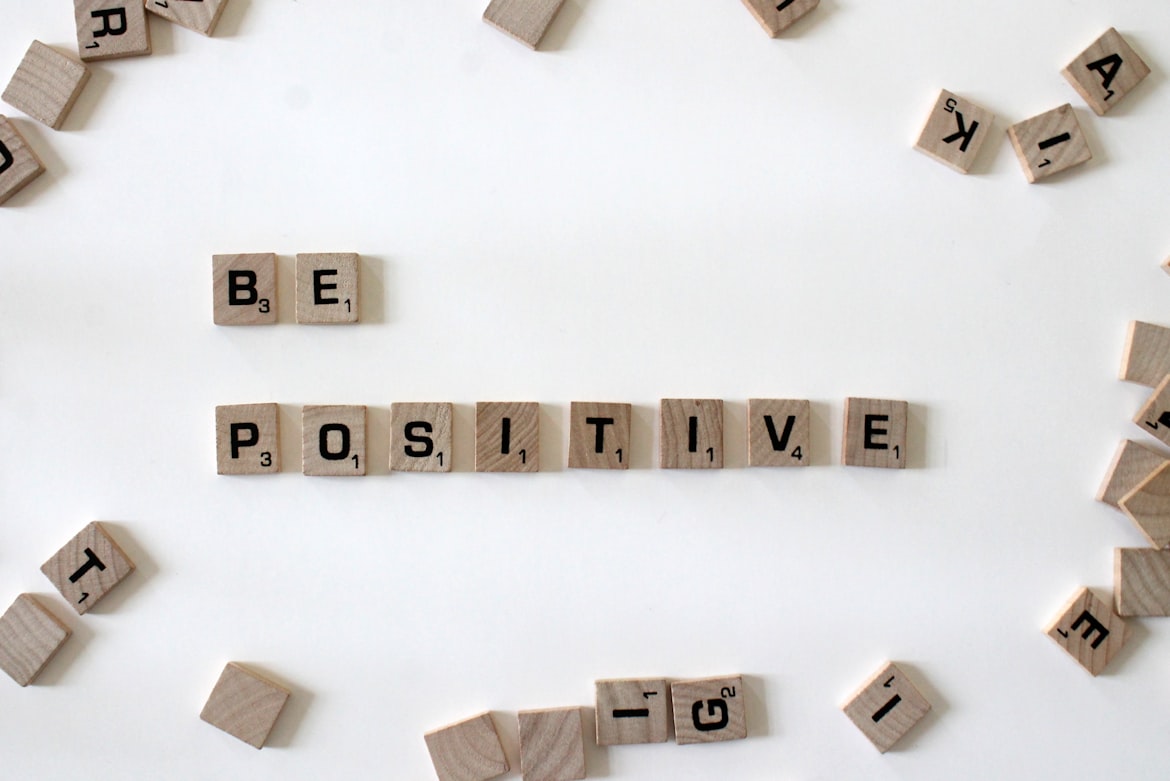
保育士に向いている人になるコツは、ずばり 努力と経験です!!
最初は向いていないと思っていても、日々保育士として働くことで、そして良い先輩保育士に指導してもらえることで、自分自身の成長になります。
自分の考え方を一度見直して、ポジティブにとらえてみませんか?
もし、あなたが保育士に向いていないかもと悩んでいて、子どもは大好きで保育士という仕事が好きな人。
それはあなたではなく、働く園の原因かもしれません。
良い保育園で、自分の保育観に合った働き方をすることで、保育士として自身が持てるようになりますよ。
悩んでいる方は転職も視野にいれて考えるのも必要です。
転職エージェントは登録無料です。
転職に関してはこちらの記事もお読みください 。

保育士に向いている人の特徴まとめ
- 保育士に向いている人の特徴はたくさんあるが、人間得手不得手がある
- 保育士に向いていない人でも努力次第で向いている人になれる
- 保育士に向いていないのではなく、職場が自分に合っていない可能性がある
- 保育士としての経験を通して保育士に向いている人になれる!!
保育士に向いている人も向いていない人も努力次第と経験で保育士として成長できること間違いなし!です。
保育士を目指している方は、あきらめず保育士として働く中で向いている特徴をつかんでいきましょう。
子どもたちの成長に寄り添える、本当に素敵な仕事です。
みなさんにとって働きやすい環境で、楽しんで保育士という仕事ができますように。
少しでも参考になると嬉しいです。
最後までお読み下さり、ありがとうございました。

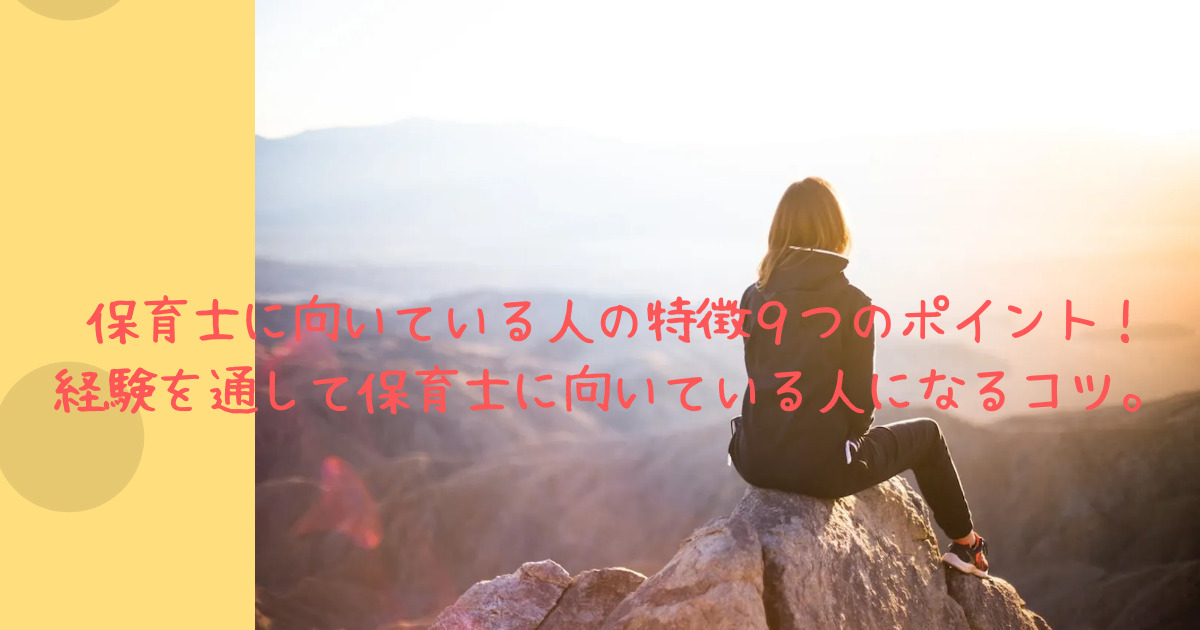
コメント