 保育士なこ
保育士なこ嚙みつきって?
どんな時に起こるの?
1歳児から2歳頃に多く見られる噛みつき。お友達とのかかわりの中で噛んでしまい傷跡が残ってしまうこともあるので、出来るだけ防ぎたいものですよね。
噛みつきのメカニズムや、保育士が実践している予防法、噛みつきが起こった際の対処法を紹介します。

噛みつきはどうして起こるの?噛みつき行動について
自我が芽生え始める1歳から2歳の時期は、「こうしたい」「あれがほしい」などの欲求が強くなってきます。その中で自分の使っていたおもちゃを友だちに取られたり、友だちが使っていたおもちゃを欲しくなったりして自分の欲求が通らないときに言葉の代わりにとっさに「噛みつき」という行動がでてしまいます。

上手く気持ちを言葉にできない
気持ちが上手く言葉で表現できない・・・おもちゃを貸して欲しくても意思表示が出来なかったり「貸して」と意思表示しても貸してくれなかったりするとその嫌な思いを噛みつくことで意思表示をしてしまうことがあります。
どうやってかかわったらいいかがわからない
お友達と仲良くしたい気持ちや、興奮してしまってどうしたらいいか分からず噛みつくなど、不満が原因で噛みつく子どももいます。
保育士は理由があるトラブルでの噛みつきのほうが分かりやすく噛みつき行動を止めやすいです。

人間の発達の関係性
人間の体は「上から下」に発達するといわれています。1~2歳児の場合には、手以上に口が発達していることもあり、とっさの際に口が先に出てしまう傾向にあります。
噛みつきを予防するには?
子どもには「噛みつくこと」=「悪いこと」と言う認識はありません。
そのためできるだけ目を離さずに見守り、噛みつきを未然に防ぐことが大切です。
ストレスが噛みつき行動を引き起こしている事もありますが、愛情をしっかり注いでいても噛んでしまうことはあります。
また、クラスの中で一人目の噛みつきを出さないことも重要になってきます。なぜかというと、噛まれた子が覚えて次に同じような場面の時に他の子を噛む可能性があるからです。子どもは覚えて同じ行動をする事があります。

噛みつきを予防するポイント
- 子ども同士の距離をとるようにする。
- 同じ玩具を複数用意しておく。
- 子どもがトラブルにならないよう玩具を増やし、一か所に集まらないように保育室の環境を整える。
- 担任の保育士同士で連携をとり、子どもを見守る位置を工夫する。
- 噛みつきが頻繁に見られる子どもの傍に保育士がつくようにする。
- 噛みつきが多い子と1対1でのかかわりを増やしスキンシップをとるなど情緒面のフォローをしていく。
噛みついた子と噛まれた子への対処法
噛みついた子へのフォロー
噛みつきは必要な言葉や行動が分からずに出てしまうことが多いのでその気持ちを代弁してあげることが大事です。
 保育士なこ
保育士なこ「○○くん、このおもちゃが欲しかったんだね。でも○○ちゃん嚙まれたら痛いよ、泣いているよ、次は「貸して」って言おうね」
気持ちを代弁し、噛むことはダメなことを繰り返し伝えていきます。お友達の泣いている表情や傷をみせて友だちの痛い思いを伝える事が大切です。

噛まれた子へのフォロー
痛かった思いを受け止め、噛んだ子の気持ちを代弁して話してあげます。
 保育士なこ
保育士なこ「痛かったねー。○○くん○○ちゃんの使っていたおもちゃがほしかったんだって」
*噛まれた傷は内出血によるものなので、すぐに患部を冷水で冷やすか、氷嚢で冷やすことが大切です。
すぐに温めたり、患部をもんだりすると内出血が余計にひどくなってしますのでやめておきましょう。

保護者対応
噛んだ子の保護者対応
私の園では、噛んだ子の保護者には毎回は報告していません。
本当に頻繁に噛む子の保護者に毎回噛みました・・・ばかりの報告になっては保護者も保育士に対して止められていないのかと不信感がつのりますよね。
私は頻繁に噛みつき行動があるとき、何回か重なって情緒不安定になっているときなど、そのときそのときに判断して、保護者に伝えるようにしています。
「最近園で、噛みつきが増えてきているのですが、家ではどうですか?どうしてもおもちゃが欲しい時などに、上手くまだ言葉で言えないので噛みつきが出てしまうようです。私たち保育士も○○くんの気持ちを受け止めながらしっかりみていくようにします。ご家庭でも少し変わったことなどあれば教えてくださいね。」
噛まれた子への保護者対応
噛まれた子の保護者にはケガなのでしっかりと状況を伝え報告します。乳児の場合は止められなかったこちらの責任でもあるので、しっかりと謝罪することが大切です。
今日「○○ちゃんの遊んでいたおもちゃが欲しかったようでお友達に噛まれてしまいました。防げずに大変申し訳ありません。すぐに冷却していますのでおうちでも様子を見てあげてくださいね。お友達にも言葉で言えるように伝えています。すみませんでした。
初めて子どもを園に通わせる保護者は噛みつきの行動を知らない保護者もいます。それを知らせることにより園に対しての不信感を抱かないためにも、入園の際にしっかりと保護者に伝えておく必要があります。
私が入園の時に必ず保護者に伝えている事です。噛みつきとひっかきの話です。

子どもたちに自我が生まれてくると、噛みつきやひっかきが始まったりします。「それ、ぼくの」「ほしいな」「いやだ」など、こういった気持ちがあってもまだ言葉にはなりません。
だから、噛みついたり、ひっかいたりしてしまいます。また、目の前に出てきた誰かの指や顔に、手や口が出ることもあります。
これは成長発達のひとつの特徴です。
子どもたち全員がするわけではありませんが、誰かを傷つけようという気持ちもありません。逆に「すき」「あそぼう」と、他児に対する興味から噛みつきやひっかきのような行動にでることもあります。
私たちも、幼いながらも言葉で表現できるように働きかけています。おもちゃを取ろうとし始めたら「使いたいのかな?かしてって言ってみて」と伝えますし、顔の前に手を出したら「どうしたの?」と声をかけて、お子さんの気持ちをくみとるよう努力します。
けれども、声かけや働きかけが間に合わないこともあります。できる限り止めて、気持ちを受け止め、言葉にするように伝えます。
もしも、ひっかきや噛みつきが起きてしまったときは、適切に処置して、保護者の方にもお伝えします。もし、ご家庭でもそのような様子が見られましたら、お知らせ頂きたいと思います。
ご理解のほどよろしくお願いします。

 保育士なこ
保育士なここういう働きかけをする事で保護者との信頼関係ができ、噛みつきが起こった時も保護者に理解してもらいやすくなります。
まとめ
乳児に多い噛みつき、特に1歳児の担当の保育士は毎回頭を悩ませると思います。
時期的なものですが、一人一人の子どもの気持ちをしっかり受け止めながら接していくと、いつか必ずなくなっていくものです。
日々の環境を見直し、子どもたちが安全で楽しく過ごせるように保育していきたいですね。
少しでも参考になると嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました♥

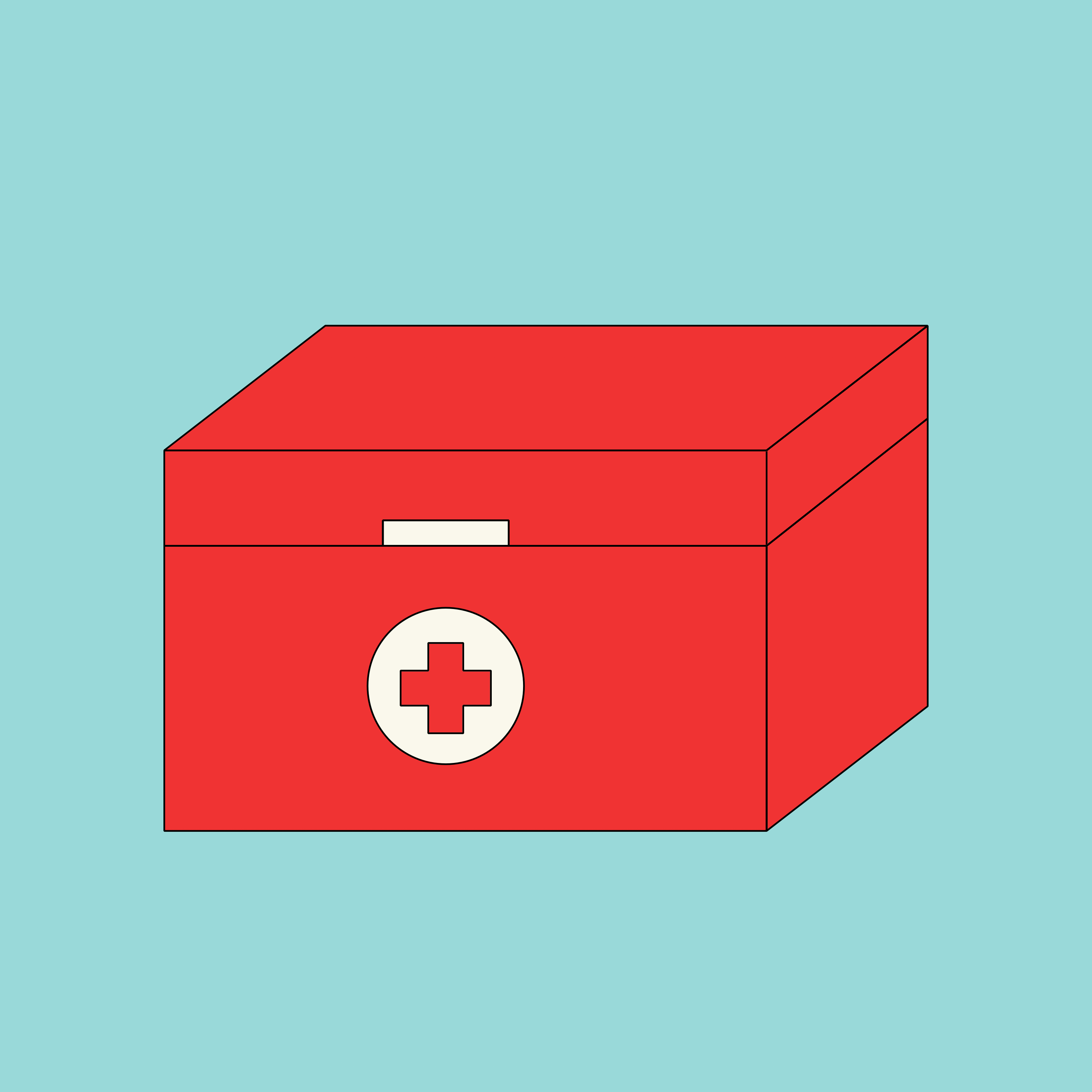
コメント